
Contents
1.中小企業の社長がマネジメントや人材育成を苦手だと感じる理由は
「毎期、掲げている売上目標が達成できていない。常に未達に終わっている。
売上目標の達成のためにも、マネジメントの強化や人材育成が必要なのではないか?と思うことがある。
一方で、仕事は好きだけど、マネジメントや人材育成はどうも苦手だ。」
そんな風に感じることはありませんか。
実はこれは、中小企業の多くの経営者に共通する悩みです。
その理由の一つは、経営者の経歴にあります。
多くの経営者は、営業系、または技術系や生産系の出身です。
もともと営業をされていた社長は営業が得意です。
技術系や生産系の社長は、技術や生産が得意です。
本業が得意な人が起業して経営者になっているケースが多いのです。
考えたら、当たり前の話ですね。
二代目経営者や三代目経営者の場合も同じです。
営業または、技術・生産などの本業に長く携わってきた方が多いのです。
営業(または、技術・生産など)が得意な一方で、マネジメントや人材育成については特に習う機会がなかった…という方が多いです。経験値も必ずしも豊富ではないでしょう。
体系的に習っておらず、経験値も低ければ、不得意なのは、いわば当たり前の話です。
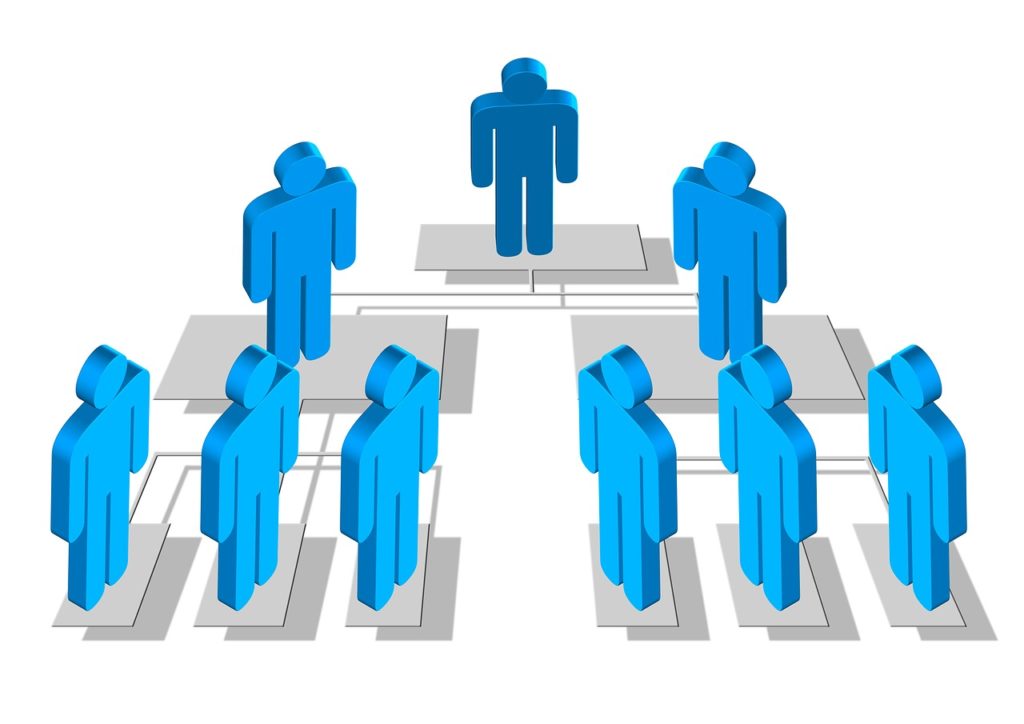
とは言っても、社長の立場になると、マネジメントや人材育成をまったく避けて通ることはできません。
社員に仕事を割り振ったり、仕事の指示を出したりします。
改善提案などの前向きな意見を社員に求めることもあるでしょう。
ところが、社員の方は、言う通りにできないのか。やる気がないのか。
必ずしも指示通りには動いてはくれません。
なぜ、指示したことをさっさとしないのだろうか。
社長はイライラすることになります。
あるいは、指示したことはするけれど、指示したことをするだけで、自発的には動かない。
主体的に自分で考えて動くこともしない。
社長はまたイライラします。
こんなことまで、いちいち言わないといけないのか。
これくらいのこと、なぜ、自分で考えて動こうとしないのか。
普通これくらいのこと、考えたらわかるだろう。
営業は得意なのに(または技術や生産は得意なのに)マネジメントや人材育成がうまくいかないので、ストレスに感じるのです。
社員が指示通りに動かない場合、注意したり、叱責したりするような場面もあるでしょう。
人に注意すること、叱責することは誰にとっても、ストレスの要因です。
つい言い過ぎて、自己嫌悪を感じるようなこともあるかもしれません。
あるいは、自分は会社の先行きにこんなにも危機感や焦りを感じているのに、なぜ社員はみんなノホホンと気楽に構えているのか。歯がゆく感じることもあるでしょう。
何度も言っているのに、なぜ自分の考えや思いが社員に伝わらないのか。
社長には理解ができません。
こうして、仕事は好きなのに、社員に向き合ったり教育したりするのは、苦手だ。
好きではないと思うようになってしまうのです。

2.マネジメントや人材育成が苦手だと感じる社長が陥りがちなパターンとは
そんな社長が陥りがちなパターンがいくつかあります。
(1) 社長がプレイングマネージャーになってしまっているパターン
まず、一つ目は、こんな社員には仕事を任せられないと感じ、いつまでもプレイングマネージャーとして自分が仕事をしてしまうパターンです。
もともと社長が優秀で、仕事が好きな方が多いということも、このパターンに陥りやすい理由の一つです。
社長が一プレイヤーとして仕事に注力してしまうことから、社長自身が日々、仕事に忙しく、社員としっかりコミュニケーションを取って、育成することに十分な時間を割けません。
結果的に一方的な指示や断片的な指示が多くなりがちです。
社長の頭の中には、もちろん、その指示の背景や意味などがしっかりあります。
ところが、指示された社員には、その全体像が必ずしも伝わっていません。
そもそも、社長と社員では、持っている情報量自体に開きもあります。
そこから、社長と社員の間で、認識の不一致が起こります。
そして、認識の不一致は、行動の不一致を引き起こします。
こうして、ますます、社長から見て、指示通りに動かない社員が多い。自発的、主体的に仕事しない社員が多い。という状況が強化されてしまいます。
これが、ありがちな一つ目のパターンです。

(2) 取り組みが持続せず中途半端になっているパターン
ありがちな二つ目のパターンは、社長がマネジメントや人材育成の必要性を認識していながら、うまく進んでいないというパターンです。
この場合は、会社として、たとえば経営理念を策定したり、ミーティングを開催したり、人事制度を作ったりします。ところが、その効果がすぐには現れないことがあります。
理由はいくつかあります。
日頃のコミュニケーション不足から、そもそも社長と社員の間の信頼関係が構築されていないことが理由になっている場合があります。
また、理念策定やミーティング開催などの進め方が適切でないために、社員に意図がうまく伝わっていない場合もあります。
効果が現れないのは、そもそもの信頼関係の不足や進め方の問題なのですが、社長にはうまくいかない理由がよくわかりません。
そこで、「うちの社員には理念は響かない」と思ったり、
「社員のレベルが低いから、うまくいかないのではないか…」と思ってしまうのです。
そうすると、せっかく始めた取り組みもなかなか続きません。いつの間にか、やめてしまったり、中断していたり、不徹底になりがちです。
社員は、そうした社長の姿を見ています。
こうしたことが続くと、「社長が何か思いついても、またすぐやめるだろう」と社員に思われるようになります。
その結果、社長から見て、社長の言葉に「社員がますます響かなくなってしまう」のです。
これが、ありがちな二つ目のパターンです。

3.このままでは会社が成長しない…と思ったら
では、どうすればいいのでしょうか。
少数精鋭の組織を前提に、社員を増やさない、というのも一つの選択肢でしょう。
そうではなく、やはり会社を成長させたい。
そして、このままでは会社が成長しない…と思ったら、その時がマネジメントや人材育成を考える一つのタイミングです。
数人程度の企業規模であればともかく、社員が増えてくると、マネジメントや人材育成がなければ、企業は機能しません。
(1) このままでは会社が成長しない…と思ったときにやるべきこと
具体的には、たとえば以下などが必要になります。
・そもそも、なぜ会社を成長させたいのか。会社として、何を目指すのか。何のために仕事するのかという理念やビジョンの明確化と共有。
・社員が思うことが言える安心・安全・ポジティブな組織づくり。基本的な信頼関係の構築。
・数字にもとづいた意思決定を行うための仕組みづくり。
・社員に報酬還元できるしくみづくり
・PDCAサイクルの徹底(計画-実行-ふり返りと計画への反映の一連のサイクルを継続し、定着させる)
このようなことが必要です。
では、こうしたことをどのように進めていけばいいのでしょうか。
(2) 具体的な進め方を考えるときの3つの選択肢
具体的な進め方としては、以下の3つの選択肢があります。
まず一つ目は、社長が苦手を克服して、社長主導で行うという選択肢です。
社長が苦手を克服し、変わろうとする真剣な姿から、社員に社長の本気の覚悟が伝わることでしょう。
二つ目は、マネジメントや人材育成に長けた経営幹部を新たに雇用するという選択肢です。
社長が苦手なことの克服に時間やエネルギーを注ぐよりも、得意な人と二人三脚で進める方が早く、かつ効果的に物事を進められます。
ただし、中小企業の場合、マネジメントや人材育成に長けた経営幹部候補を見つけ、雇用することのハードルは低くはありません。できたとしても、相当、高額な給与の支払いが必要になります。
また、新たに経営幹部として雇用した、ハイスペックな人材と元からの社員がうまく融和せず、新規雇用した人の能力が十分に発揮されないケースがあります。経営幹部を新たに雇用する場合は、能力だけでなく、人間関係にも配慮が必要です。
三つめは、外部からのサポートを受けるという選択肢です。具体的にはコンサルティング契約です。この時に、注意が必要な点が2点あります。
留意点の一つ目は、なぜ、会社を成長させたいのか。会社として、何を目指しているのかというビジョンの明確化・言語化から関われるコンサルタントが望ましいということです。
なぜならば、マネジメントや人材育成は会社の基盤づくりです。基盤を整えて、会社として何を目指すのかというビジョンが明確であってこそ、より効果を発揮するものだからです。
逆に言うと、ビジョンが明確でないまま、マネジメント強化や人材育成を進めようとしても、判断の基軸が明確でないために考え方の一貫性や納得性を保ちにくいでしょう。
企業のビジョン実現のために、マネジメントの確立や人材育成を行うという視点が必要です。
留意点の二つ目は、ビジョン実現を前提として考えた場合、短期の課題解決型コンサルティングではなく、社外幹部として長期的・継続的に企業に関わるパートナー型のコンサルタンティングが有効ということです。
会社のマネジメントの確立や人材育成には、一定の時間がかかります。
長期的・継続的な関わりによって、持続的な取り組みを行うことが望まれます。

4.あなたの会社が成長しない5つの理由とは
会社が成長しない理由5つをまとめると以下になります。
① 社長がプレイングマネージャーになってしまっている。
② 社員が増えているのに、マネジメント強化や人材育成に取り組んでいない。
③ マネジメント強化や人材育成の取り組みが持続せず、中途半端になってしまっている。
④ ビジョンを明確にしないままに、マネジメント強化や人材育成の取り組みを進めており、一貫性や納得性が不足している。
⑤ 短期的なコンサルティングで解決しようとしている。
思い当たる項目はいくつあったでしょうか。
5.マネジメント強化策としての意志決定の仕組みづくりとは
最後に、意志決定の仕組みづくりについて少し補足します。
経営数字のデータが整備されていない企業では、自社がどこで儲けていて、どこで損しているかがよくわかりません。うまくいっているときは、このような状況でも特段、問題にはならないかもしれません。
ところが、たとえば赤字になったときなどに、数値データが整備されていなければ、どこをどう改善すればいいかという判断ができません。
的確な意思決定を行うには、必要な数字をタイムリーに把握できることが必要です。
なお、経営者にとって、必要な経営数字とは、決算書や試算表の詳細な分析ではありません。
経営者が学ぶべきお金の話と学ぶべきでないお金の話があるのです。
そんな内容を毎月、少人数型セミナーでお伝えしています。
※セミナー詳細の確認とお申込みは以下からどうぞ。
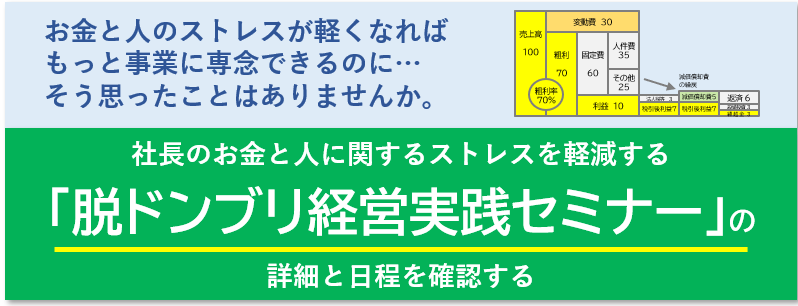
ビジョンを明確にして、社員と共有し、会社を成長させたい経営者の方の参加をお待ちしています。



























